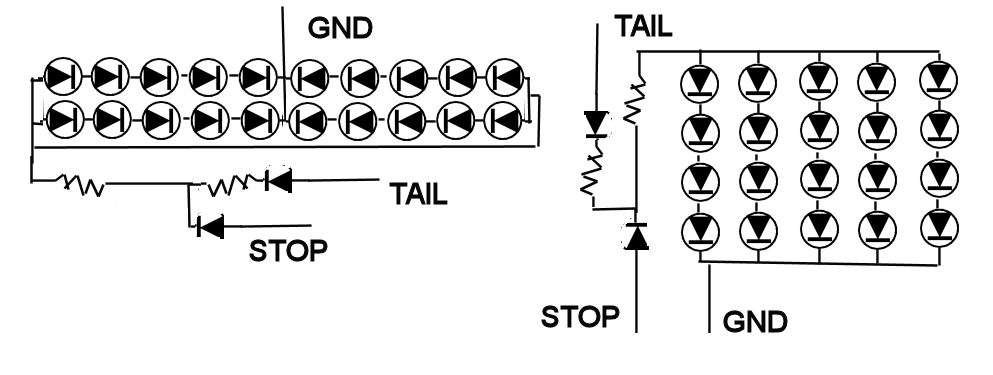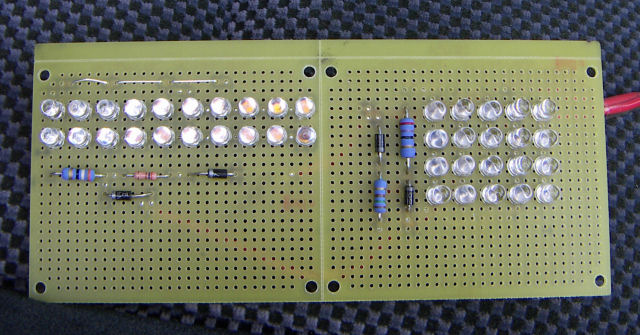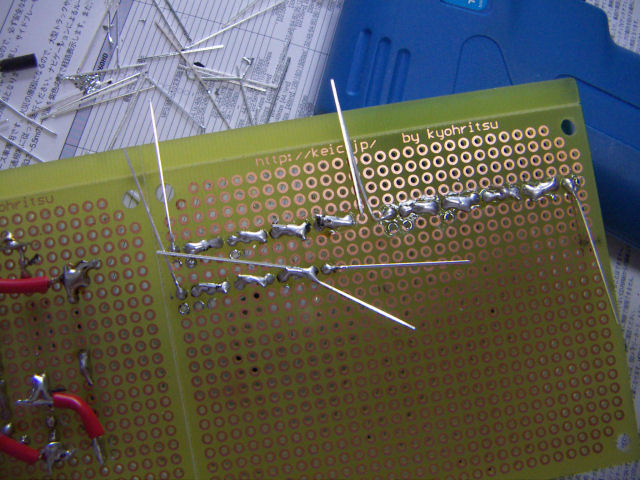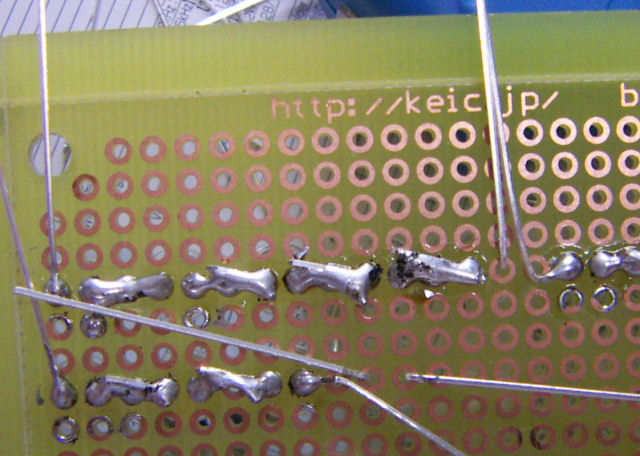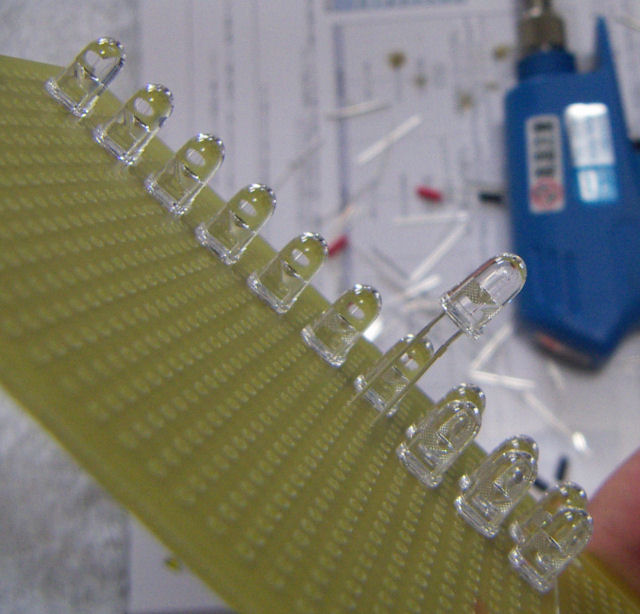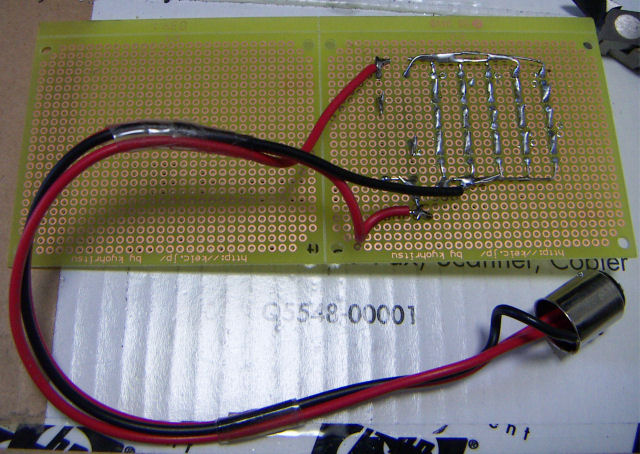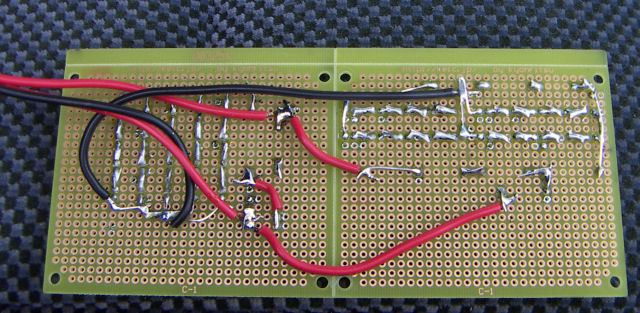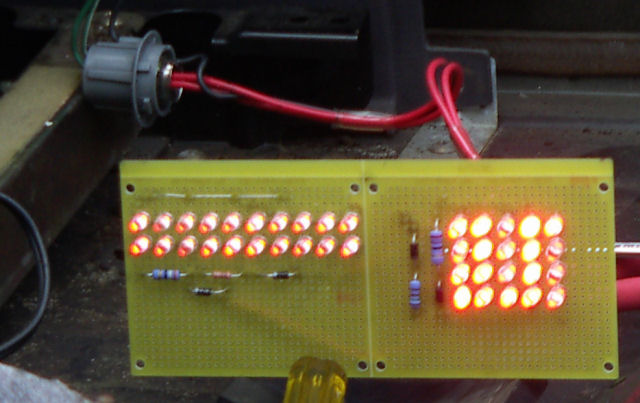エクリプスのテールを適当にLED化する
お約束:合言葉は自己責任。
工程
その2:基板作成
2-1 LEDレイアウト思案
まず作成キットのWebページにある回路図を参照してください。
ただ、SHD-HBR01は直列5個x4に回路構成が変更されているそうなので、それを頭に入れます。
ユーロテールみたく丸型にしたいひとは頭を抱えるでしょうが、
わたしは丸テールは好みではないのでどうでもいいのです。
(てゆーか丸テールはスカイラインの専売特許でしょう普通)
むしろ、アルファロメオのような糸目テールがやりたかったのですが、
以前のLED(台湾OASIS)は直列4個x5列なので、回路上美しいレイアウトにできず、
しかたなしになんの変哲もない長方形にしました。
今回のSHD-HBR01なら、5x4の回路構成なので、
長細く10x2段に並べても回路的に楽です。
というわけで、内側にSHD-HBR01(5個直列)、外側に台湾OASIS製(4個直列)のレイアウトです。
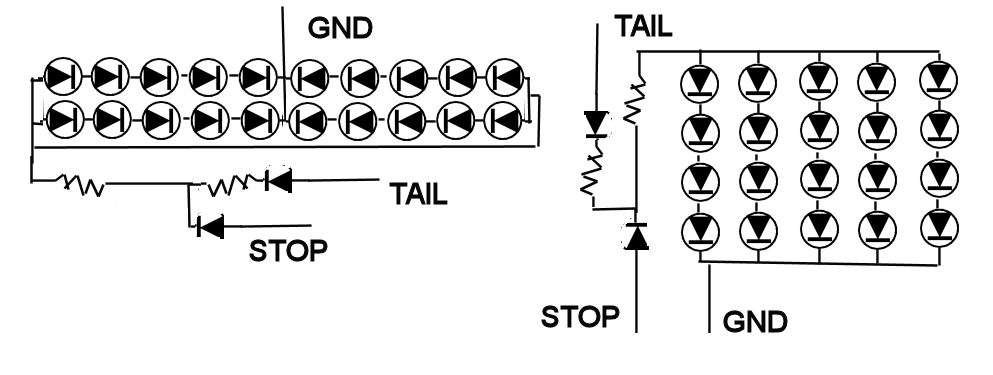
抵抗の記号が落書きっぽいのは仕様です。
で、実装するとこんな感じになります。
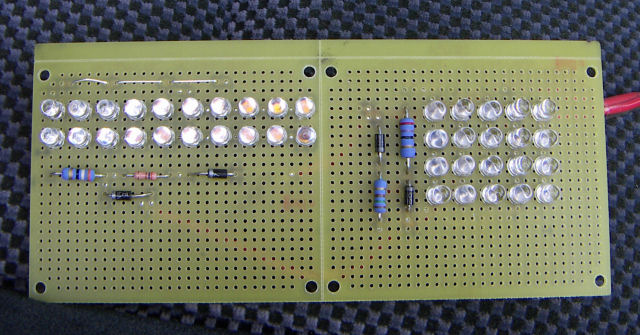
2-2 ハンダ付けしやがれ
まずLEDをひたすらハンダ付けします。
電子工作の本などでは、背の低いパーツからハンダ付けするように書かれていますが、
今回の製作の場合、LEDの配置の仕上がりがすべてを決定してしまうので、
ともかくLEDを先にハンダ付けしてしまいます。
足は浮かさずにきちんと押さえこんで固定するのが、向きのばらつきをなくすコツです。
これが高いLEDになると、放熱板が内蔵されていて背面に放熱孔をあけないといかんとか
表面実装しか対応してないとか面倒すぎなんですが、
ただの2本足のLEDならこのへんのことは考えなくてすみます。
LEDのハンダ付けが済んだら、よく眺めて傾きなどがないか確認します。
あ、LEDは極性があるので逆向きハンダ付けはNGです。
LEDのハンダ付けが終わったら、足をまとめつつ、抵抗とダイオードを足していきます。
ちなみにわたしは1回配線を間違えました。みなさんも気をつけましょう。
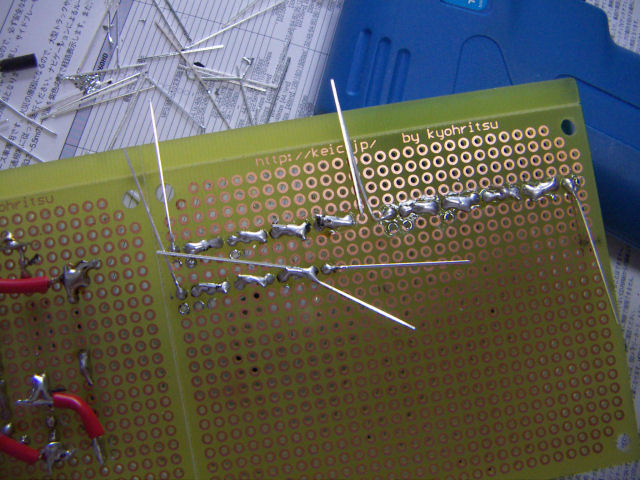
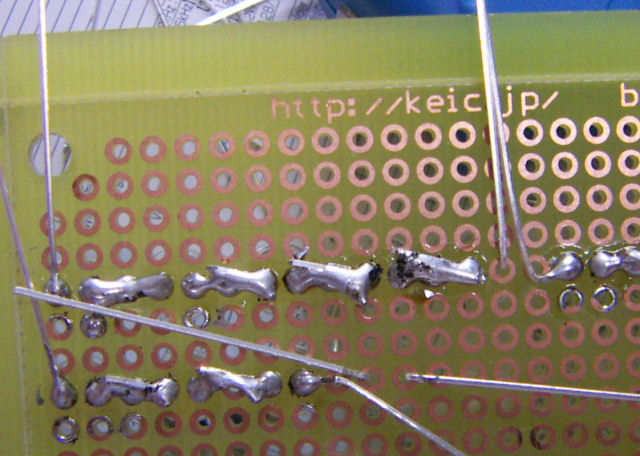
配線中の写真。LEDは1つづつハンダ付けしたほうがLEDがへんな向きになりにくいです。
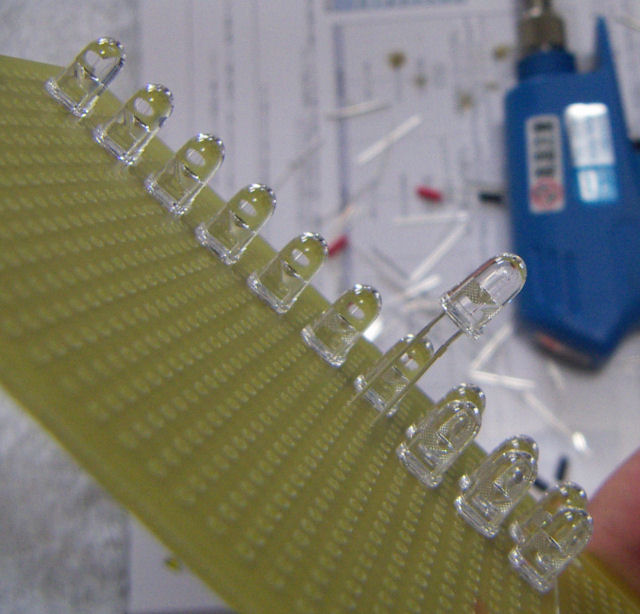
側面図。
2-3 口金に配線
惜しい事に、口金の端子のどっちがストップでどっちがテールかの情報は
しまりす堂HPにも書いてません。
が、そこからのリンクページに
解説がありました。
このサイドピンと端子の位置関係からストップ、テールの各端子の位置を把握して配線します。
あ、もちろんGNDも。合計3本です。
基板からの線は12cm程度にしました。別に理由があるわけでなく、適当です。
なお、スピーカケーブルの買い置きを使いました。
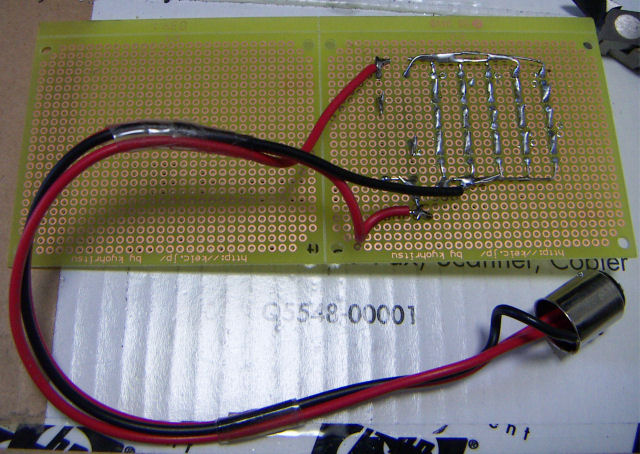
これはまだLEDを1組だけ使って作成したときのやつですが、一応口金取り付けの参考として。
なお、基板上の配線がまだミスってる時代のです。
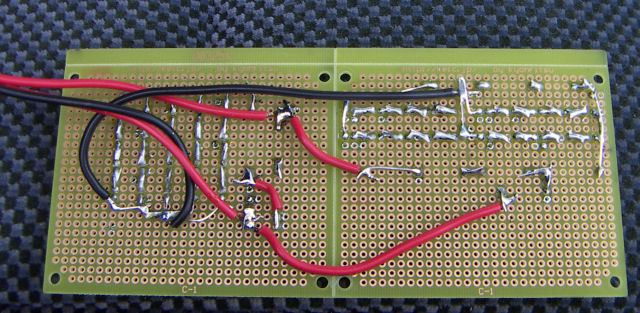
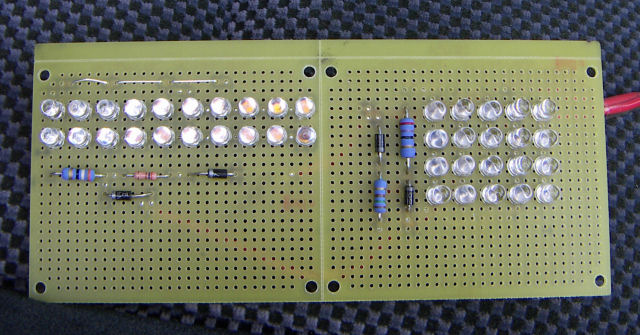
ハンダ付け完成図:右テール用
基板が完成したら、組み付ける前にテストしてみます。
口金を利用しているので、サービスホールから電球を引っ張りだして取り付ければOKです。
電球は片側2個とも取り外してから試しましょう。
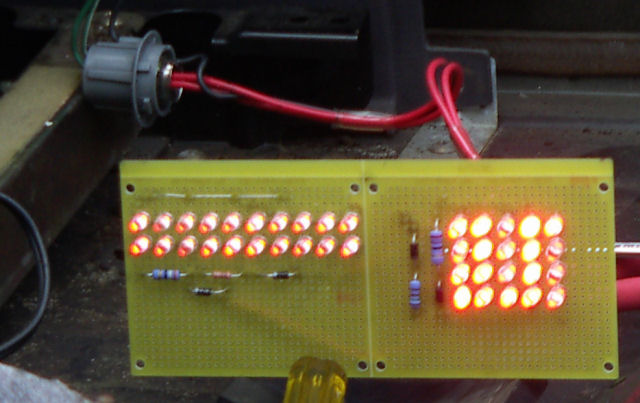

リフレクターとかなくてもこれくらいは光ります。
前:工程1:次:工程3